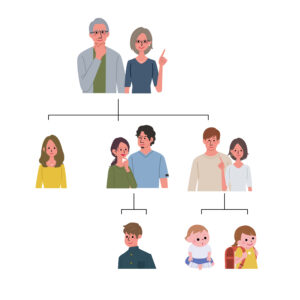相続申告の流れ 相続税申告や小規模宅地等の特例


相続税申告が必要となる方や、相続税手続きの流れ、小規模宅地等の特例など、相続申告の流れについてお伝えいたします。
相続税申告が必要な方
どのくらいの財産を所有していれば、相続税の申告が必要でしょうか。
相続税は原則として、遺産の評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
基礎控除額は、次のようになります。
3000万+(600万×法定相続人)
ただし、小規模宅地の評価の特例等による減額を受けることにより、遺産の評価が基礎控除額
以下になる場合は、相続税の申告が必要です。
相続税手続きの流れ
相続開始後の申告手続きスケジュール
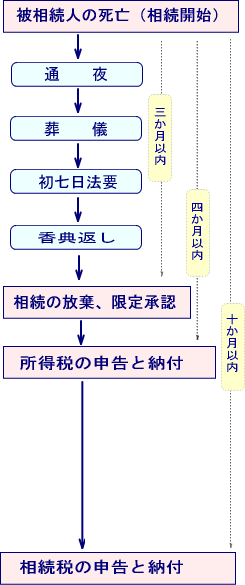
- 死亡届の提出
死亡届は、7日以内に市区町村に提出します。 - 葬式費用の領収書の整理・保管
- 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。
- 四十九日法要のころ行われます。(相続財産から控除する葬式費用とはなりません)
- 遺産や債務について、概要の把握
相続を放棄するかを決定します。 - 相続人の確認
被相続と相続人の戸籍謄本を取り寄せます。 - 被相続人の死亡した日までの所得を申告します(準確定申告といいます。)
- 遺産や債務の調査
- 遺産の評価・鑑定
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告書の作成
納税資金の準備、延納又は物納の選択もあります - 被相続人の死亡した時の住所地の税務署に相続税の申告、納税を行います。
- 不動産の相続登記、預貯金等の名義書換えを行います。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住や事業のために使用していた土地は、相続人の生活基盤になる財産であり、
処分しづらいことから、一定の面積までは評価を軽減する特例が小規模宅地等の特例です。
- 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等であること。
- 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること。
- 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。
- 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等が限度面積までの部分であること。
この場合の限度面積とは、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。- 選択した宅地等が、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・・・・400平方メートル - 選択した宅地等が、特定居住用宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・・・・240平方メートル - 選択した宅地等が、特定同族会社事業用宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例の対象
となる宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・・・・200平方メートル - 選択した宅地等すべてが、特定同族会社事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積
特定同族会社事業用等宅地+特定居住用宅地等の面積×5/3+特例対象宅地等の面積×2
≦400平方メートル
(注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が2人以上であるときは、
その宅地等を取得した人全員の選択についての同意が必要です。
- 選択した宅地等が、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等である場合
- 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。
ただし、その宅地等が申告期限までに分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当
することになったときは、この特例の適用を受けられます。 - 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。
ただし、その宅地等が申告期限までに分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当
することになったときは、この特例の適用を受けられます。
- 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合
- 相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割
されたとき
(注) 上記の場合には、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に税務署長に対し、 更正の請求書を提出することができます
減額割合
評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。
- 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び
特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80% - 1に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50%
適用除外
なお、この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人
(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、
特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)の適用を受けている場合
などには適用されません
参考:国税庁ホームページ